はろー!けーけーです。
「同僚をランチに誘えない」
「帰り道に『飲みに行かない?』って言い出せない・・・」
「エレベーターで同僚とばったり会ったけど、『一緒に帰ろう』と言い出せず、行きたくもないトイレに行ってタイミングをズラした…」
これらは本当にあった僕の実体験です。
こんな風に“人を誘えない”ことで悩んでいる方は、意外と多いのではないでしょうか?
今回はその理由と、どうしたら「人を誘えない」という事実と向き合えるのか?を解説します。
- 人を誘うことが出来ない自分のコミュ力の低さに落ち込んでいる人
- なぜ自分は人を誘う事が出来ないのか、その理由を知りたい人
人を誘えない・・・あるある場面
人を誘えない自分を痛感する場面で、代表的なものは以下の2つのシーン。
「ランチ(飲みに)に行きませんか?」と誘えない
「一緒に帰りませんか(行きませんか)?」と誘えない
僕はサラリーマンなので、日常的にこういったシーンに遭遇します。
逆に月に1回あるかどうかくらいの頻度で、人から誘われることもあります。
それはそれで、なんだかんだ言って嬉しいんですよね。
だから人を誘うこと=プラスの行動。だとわかっているつもり。
しかし自分の行動をいざ振り返ってみると、自分から誘ったことなんて数えるほどしかありません。
コミュニケーションをめちゃくちゃ取りまくりたい!
というわけではないけれど、「たまには人を誘った方がいいよなぁー」「なんで自分はこんなにコミュ力が低いのかなぁー・・・」と悩むわけです。
人を誘えない理由
人を誘えない理由を突き詰めて整理していくと、そもそも「人を誘わない」ほうが、自然なのではないかと。
なぜなら、自分の感情が揺さぶられるリスクを避けられるから。
以下のケースを考えてみてください。
例A) 自分は100%、同僚は50%の確率で誰かとランチに行きたいと思っている。自分から同僚を誘ってみたところ、一緒にランチに行くことになった。
例B) 自分は100%、同僚は50%の確率で誰かとランチに行きたいと思っている。席で待っていたところ、同僚が誘ってきてくれて、一緒にランチに行くことになった。
最終的に起こるのは「ランチに行くことになった」という同じ結果ですよね。
例AとBでは、どちらが嬉しいと感じますか?おそらく、どちらの嬉しさも甲乙つけがたいと感じるはずです。
では次のケースも考えてみてください。
例a) 自分は100%、同僚は50%の確率で誰かとランチに行きたいと思っている。自分から同僚を誘ってみたところ、断られたので、1人でランチに行くことになった。
例b) 自分は100%、同僚は50%の確率で誰かとランチに行きたいと思っている。席で待っていたところ、同僚からは特に声をかけられなかったため、1人でランチに行くことにした。
こちらも最終的には1人でランチに行く、という同じ結果です。
例aとbでは、どちらが悲しいと感じますか?この場合はaの方がよりショックが大きくて、むなしく感じませんか?
つまり、自分から誘う=能動的、相手から誘われる=受動的、と言い換えた場合、能動的である方が感情が揺さぶられるリスクが高く、受動的でいた方が低い。
“プラスの結果”と”マイナスの結果”のあいだにある感情の落差は、自分が能動的な場合にはより大きく、受動的な場合にはより小さい。
こんな風に言えます。
心理学の専門家では無いので、詳しい理由はわかりませんが、おそらく予測のつかない自然環境の中でヒトが生き延びるためには、能動的な面を抑えるように調整されていた方が有利だったのではないでしょうか。
というわけで、「人を誘えない」というのは特別でもなんでもなく、リスクを避けようとするヒトという生き物にとって、普通の感覚だということに気がつきました。
人を誘った方が良い理由
では何故この社会では「人を誘った方がより良い人生送れそう」な感じがするのか?
もうお分かりかもしれませんが、「人を誘う側になった方が、プラスの結果に出くわす可能性が高くなるから」です。
もういちど例A〜bまでを書いてみましょう。
**例A)** 自分から同僚を誘ってみたところ、一緒にランチに行くことになった。
**例B)** 席で待っていたところ、同僚が誘ってきてくれて、一緒にランチに行くことになった。
**例a)** 自分から同僚を誘ってみたところ、断られたので、1人でランチに行くことになった。
**例b)** 席で待っていたところ、同僚からは特に声をかけられなかったため、1人でランチに行くことにした。
この世界では、自分も含めて全員が平均50%の確率で「誰かと一緒にランチに行きたい」と思っていると仮定します。
1日ごとに「行きたい」と「行きたくない」が変わるイメージ。
現実もまあまあそんな感じでしょう。
ここで注意しないといけないのは、50%は「誰かと一緒にランチに行きたいと思っている」確率であって、決して「実際に誘ってくる」確率ではないのです。
上で書いたように「誘わない方が普通」なので。
だとすると「行きたいと思ってて誘う」「行きたくないけど誘う」「行きたいと思ってるけど誘わない」「行きたくないし誘わない」という4つの集団のうち、世の中で1番多いのは、「行きたいと思ってるけど誘わない」または「行きたくないし誘わない」のはず。
そうであれば、1番高い確率で良い状況に身を置けるのは、「行きたいと思ってて誘う」という集団にいることです。
ここでいう良い状況とは、「(自分が)行きたい × (相手も)行きたい」というお互いがプラスの状況。
要するにWinWinってやつ。
少なくとも自分から「行きたいと思ったときは誘う」ようにすれば、あとは相手が行きたいかどうか、50%の高確率なギャンブルになるというわけですね。
しかしながら、「誘わない」側にいる限りは、周りの人からも誘われない可能性が高い。なぜなら、誘う側にいる人のほうが少ないから。
そうすると必然的に、「(自分が)行きたい × (相手も)行きたい」というプラスの状況に身を置ける可能性は低くなってしまいます。
改めて考えてみるとけっこう単純ですが、この社会で「人を誘った方がより良い人生送れそう」なのはほぼ正しい事実のようです。
人を誘えない自分との向き合い方
「人を誘った方がより良い人生送れそう」なのは解ったけど、じゃあどうすればいいの?
ヒトがリスクを回避する生き物である以上、人を誘わない方がむしろ自然だと先に書きました。
ですが僕たちは、心の中では「気軽に人を誘える自分でありたい」と思っています。
そうすると何が起きるか?
この矛盾した状況に理由をつけるために、無意識のうちに自分で自分を騙しはじめます。
「相手が忙しそうだ」とか「さほど親しくないし」「たぶん面白くないから」などなど。
いかにもそれっぽい理由をでっちあげて、状況に対して自分を無理やり合わせに行くのです。
しかもタチの悪いことに、自分ではそのことに気づけない。
そこで僕は、なるべく意識的に以下のように考えることで、人を誘える自分に持っていくようにしています。
人を誘える自分になるための思考その1)「嫌いじゃないよ」のメッセージだと考える
誰かを誘うとき、相手に対して好意を持ってないとダメだと思ってませんか?
「特に親しいわけじゃないし」とか「嫌いじゃないけど話が合うわけでもないし」とか。
でも実際はそんな必要まったくないです。
好きでも嫌いでもどちらでもない相手と、ランチを一緒に食べたり、駅までの道を一緒に帰ったりしてもいいんです。
※ここでいう「好意」とは、恋愛的な意味ではなく、性別に関係なく相手に抱いている印象という意味です。
考えてみてください。好きでも嫌いでもないと感じている人から「たまにはランチでも行きましょうよ」と言われて、悪い気がしますか?
そのときにちょうど自分も誰かと一緒にランチへ行きたい気分だったら、嬉しいですよね。
「特に好きな相手じゃないから、わざわざ誘う必要もない」は自分を騙すための方便です。
そんな風に自分を騙していると、むしろ相手に誤解を与えることさえあります。
相手が避けられていると感じてしまい、知らないうちに「ワタシ嫌われてるのかな」と、誤ったメッセージが伝わってしまう。
だから「好き」とか「親しいかどうか」とかではなく、ただ「嫌いじゃないよ」のメッセージを送るくらいの気軽さで誘っちゃえばいいんです。
頻度によっては相手が迷惑に感じる場合もあるため、適度な間隔を空けて誘うことをお忘れなく。
人を誘える自分になるための思考その2)断る自由が欲しいなら、断られる勇気を持て
人を誘って、相手に断られたら嫌な気持ちになるのは当然です。
その思いを強く感じるのは、リスクを回避するために組み込まれた仕組みではないかと書きました。
では「誘いを断る」って、対人関係において、そもそも悪いことなのでしょうか?
もし「誘いを断る」こと自体が悪なのであれば、もし自分が誘われた側になった場合に断ることも、悪ということになりますよね。
そうすると、世の中の全ての誘いを断らないのが良い世界、ということになってしまいます。
それって単純におかしい。
つまり自分が「断る自由」を保証されるために、「断られる痛み」はセットである。
そんな風に考えてみれば気が楽になります。
人を誘える自分になるための思考その4)対人関係コスパバカになってない?
「コスパバカ」って聞いたことありますか?
なんでもかんでも「コスパ」…つまり金銭的に測れる費用対効果のロジックで物事を捉えてしまい、肝心な本質を見失ってしまう人のことです。
60リットルの水で選択ができる洗濯機と、50リットルの水あればいい洗濯機があるとします。
「洗えれば充分」という解るような解らないような理屈で、コスパに優れた(と感じやすい)後者を選び、いまいち洗い上がりのスッキリしないシャツを着てるようなものです。
しかも着てる本人はずっとそれに気づけない。なぜなら前者の洗濯機を使う機会はすでに失われてしまったから・・・
人を誘わない理由を、「あの人に絡みにいったところで…」とか「一人で本でも読んでたほうが時間の無駄にならない」とかコスパ的な視点で考えていませんか?
対人関係とは、本来は無駄や手間暇がかかるものであるはず。
人を誘えない理由に上記のようなキーワードが出てきてしまったら、自分が「コスパバカ」になっていないか、点検する必要があります。
さいごに
最後まで読んで頂きありがとうございました。
気軽に誰かを誘える人を見るたび、自分はなんてコミュ力が低いのだろうと悩んでいました。
しかし今回の記事で書いたように、コミュニケーション(=接触)をなるべく避ける、という意識そのものは、自然の理に叶っているのではないかと考えています。
だからこそ、少数派である「誘う側」にいた方が良い状況に遭遇できる確率は高いはず。
自分からアクションを起こすのは勇気が要ることですが、「嫌いじゃないを伝える程度」の気軽さで誰かを誘ってみて下さい。
万が一断られた場合は、「これって自分が誘われたときも断っていいってことだよね!」と思いきり前向きに捉えると、痛みが少ないと思います。
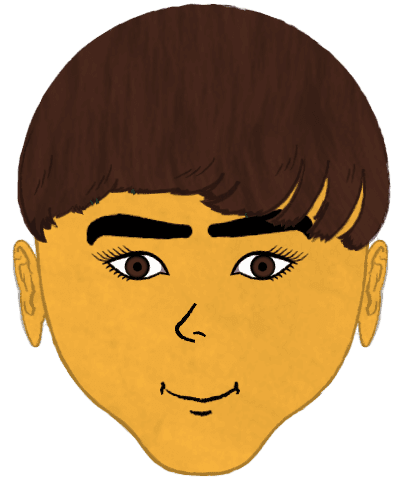 けーけー
けーけー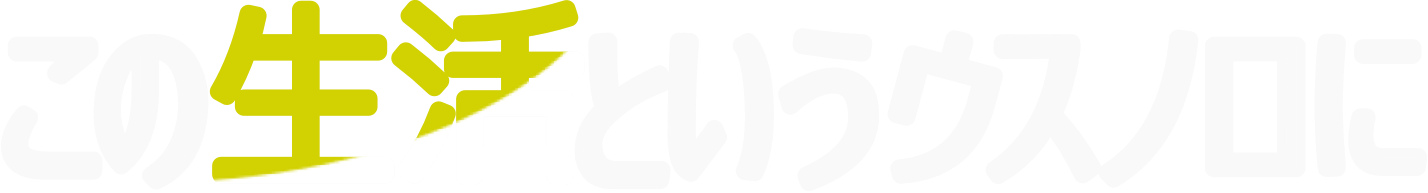

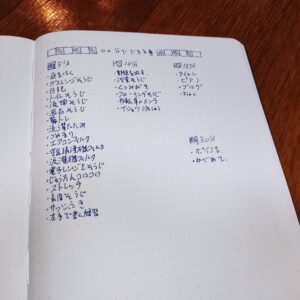

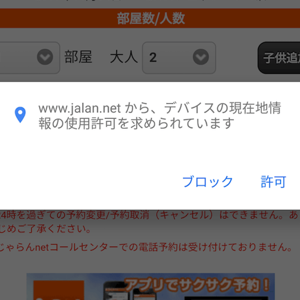
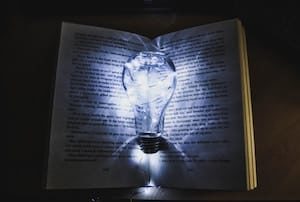
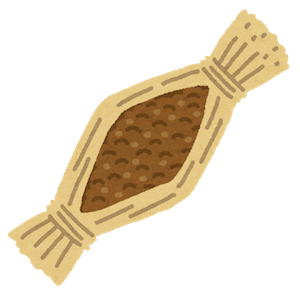
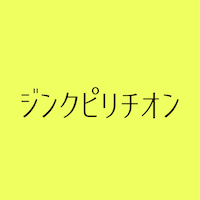
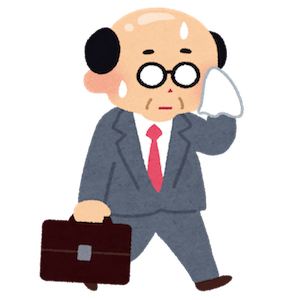
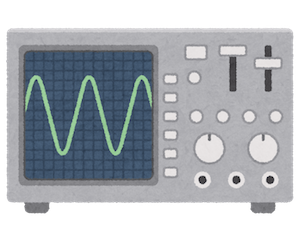
コメント